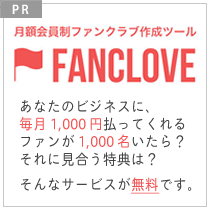2022年(令和4年)
2022年2月24日、ロシアがウクライナに軍事侵攻

日本も20世紀の初め破壊と殺戮の歴史があります。しかし、今、制裁には反発を、憎しみには憎しみを、不信には不信を、負の連鎖が先の見えない戦争へとなった。ウクライナとロシア双方に多くの死者が出ているこの戦争で、停戦への糸口がなかなか見えてこない。

国連は、198か国の国連総加盟国による『ロシアに対する軍事行動の即時停戦を求める決議案』の採択が行われた。
賛成:141か国
反対:5か国(ロシア、ベラルーシ、北朝鮮、シリア、エリトニア)
棄権:35か国(中国、インド、アラブ首長国連邦、アルメニア、カザフスタン、キリギスタン、タジキスタン、モンゴル、他)
無意志:12か国(アゼルバイジャン、モロッコ、トルクメニスタン、ウズベキスタン、他)
写真は、国連総会議場の様子で、採決の結果が電子掲示板に出ている。

3月15日(ポーランド)モラヴィエツキ首相、カチンスキーポーランド与党党首、(チェコ)フィアラ首相、(スロベニア)ヤンシャ首相の一行が列車でウクライナのキーウに入り、ゼレンスキー大統領と会談し、ウクライナへの支援を明言した。

同じことがいつわが身に降りかかってくるか、その覚悟の上での支持にはウクライナ国民に大きな励みを与えた。子どもや女性の国外退避に近隣諸国は十分な支援を続けている。

3月23日、ゼレンスキー大統領は、日本の国会でオンライン形式で現地とリアルタイムで演説した。衆参両院の議員を前に『ロシアの空爆で数十の町が破壊された。数千人が殺され、そのうち121は子供だ。』また日本の援助やロシアへの制裁について『建設的、原理的な立場をとっていただいた。アジアで初めてロシアに対する圧力をかけ始めたのは日本だ。』と謝意を示した。その上で『ウクライナに対する侵略の津波を止めるために、ロシアとの貿易禁止を導入し、各企業が市場から撤退しなければならない。』と禁輸措置を呼びかけた。
✇77年前、米軍は1945年8月6日8時15分「広島に原爆投下」、9日11時2分「長崎に原爆投下」✇

当時、広島市の人口約35万人のうち9万人から16万6千人が被爆から2~4か月以内で死亡したとされている。巨大な「キノコ雲」の写真は、投下した米軍機が撮影したもの。
1939年9月1日、第2次世界大戦が勃発。1941年12月8日、太平洋戦争が勃発。1941年9月26日、アメリカが『マンハッタン計画(原子爆弾製造)』を進め、当時「ロスアラモス国立研究所」所長のジュリアス・ロバート・オッペンハイマーがマンハッタン計画を主導した。
8月6日0時、気象観測機の「B29」3機がマリアナ諸島テニアン島の飛行場がら離陸、1時45分Mk-1核爆弾「リトルボーイ」を搭載した「エノラゲイ号」が離陸した。その後原爆の威力の記録をする科学観測機と写真撮影機の各1機、計6機のB29が原爆投下作戦に参加した。
8時12分、エノラゲイが広島市の攻撃地点に到着し、目標の相生橋に向けて8時15分原爆「リトルボーイ」が投下された。高度600m上空で炸裂した原爆は、爆心地から500m以内で即死や当日死者が99%、1㎞以内で90%の死者がでた。
当日、たまたま難を逃れた人が目の当たりにした光景は、『黒焦げになったおびただしい数の遺体』『痛いよう。熱いよう。助けて。』と泣き叫ぶ声が今も耳に残っている。『まるで地獄にいるような状況で、今でも時々夢を見ます。』と言っています。
日本政府は8月10日、スイス政府を通じて抗議文を米国政府に提出した。
「……市街地区に対し新型爆弾を投下し瞬時にして多数の市民を殺傷し同市の大半を壊滅せしめたりは……米国は国際法および人道の根本原則を無視して、すでに広範囲にわたり帝国の諸都市に対して無差別爆撃を実施し来り多数の老幼婦女子を殺傷し神社仏閣学校病院一般民家などを倒壊または消失せしめたり……従来のいかなる兵器、投射物にも比し得ざる無差別残虐性を有する本件爆弾を使用せるは人類文化に対する新たな罪悪なり……」
#広島の原爆は、ウラニウム型爆弾で、事前の爆発実験による検証がなされずに投下された。
爆風➡爆心地の爆風速は440m/s以上と推定され、音速349m/sを超える爆風で、衝撃波を伴い家屋のほとんどを破壊した。
熱風➡爆心地の地表が受けた熱線は通常の太陽の照射エネルギーの数千倍に相当するもので、地表温度は3000度~6000度に達した。
放射線➡大量のアルファー線・ベーター線・ガンマー線・中性子線の放射線の被爆者は即死また1か月以内に死亡し、5㎞以内の被爆者は放射線症により命を落とした。

8月9日午前11時2分、長崎市に2発目の原爆を投下した。当時の人口24万人のうち約7万4千人が死亡し、建物の36%が全焼または全破壊した。当初の第1目標は福岡県の小倉市(現「北九州市」)であったが、煙で視界が良くなかったことと日本の戦闘機が緊急発進したことで、第2目標の長崎市に変更した。この原爆の破壊力は広島を大きく上回り悲惨な地獄絵が繰り広げられた。
長崎原爆の破壊力は、広島の1.5倍の威力で「ファットマン」と呼ばれ、全てのものを一瞬のうちに消滅しつくした。写真のキノコ雲も巨大である。
#########################################
●米国はなぜ2度も原爆を投下したのか?
●戦争は老若男女の一般市民の大量殺戮を容認するのか!
●戦争には「正義のための戦争はない」
#########################################

1945年8月、広島に原爆を投下したエノラ・ゲイ号副操縦士ロバート・ルイス大尉が搭乗日誌書いた:
『おお神よ、我々は何をしてしまったのか。』

1947年、マンハッタン計画を主導し、「原爆の父」と呼ばれた物理学者ロバート・オッペンハイマーが原爆投下を振り返り:
『科学者は罪を知った。』

1954年3月30日、物理学者湯川秀樹が第5福竜丸被爆を受けて、毎日新聞に寄稿した「原子力と人類の転機」で:
『20世紀の人類は、自分の手でとんでもない野獣をつくりだした。』

1958年2月、原爆投下を決断したトルーマン大統領が退任5年後の米テレビ番組で:
『良心の呵責(かしゃく)を感じなかった。』

2016年5月、オバマ米大統領が広島の平和記念公園を訪れて献花後の所感で:
『我が国のように核兵器を持っている国は恐怖の論理から脱し、核兵器のない世界を目指す勇気を持たねばならない。』

2019年11月、フランシスコ・ローマ教皇が長崎市の爆心地での演説で:
『ここは、核兵器が人道的にも環境にも悲劇的な結末をもたらすことの証人だ。』
英チャーチル首相・米ルーズベルト大統領・ソ連スターリン首相が第2次大戦の終戦処理について、ウクライナのクリミヤ半島南東部ヤルタで話し合われた。
・1944年12月14日、スターリンが米国ハリマン駐ソ大使に対日参戦を条件に、満州国の
権益・樺太(サハリン)や千島列島の領有権を要求した。
ヤルタで1945年2月4日から11日まで行われた会談の中で、8日にスターリンはルーズベルトの宿泊先に訪れチャーチル抜きで双方少人数で会談した。ルーズベルトは太平洋戦争における日本の降伏にはソ連の協力が欠かせないと判断し、ソ連の要求に応じた。チャーチルは反対したが、対米関係の影響を恐れて最終的に秘密協定に同意した。
最終日の2月11日、「ヤルタ秘密協定」が文章化されて3巨頭が署名した。翌12日、ワシントン・モスクワ・ロンドンで発表されたが「極東事項」は秘密とされ、戦後の1946年2月になって明らかになった。
病弱のルーズベルトがわざわざ遠くソ連にまで行き会談に応じたことは、スターリンにと
っては主導権を握る絶好の機会であった。
会談後2か月あまりの4月12日ルーズベルト大統領は急死した。
◗1941年4月13日、「日ソ中立条約」締結。破棄の場合は1年前に通告する不可侵条約。
◗1941年8月、「大西洋宣言」米・英両首脳が第2次大戦における連合国側の指導原則
で、「戦争によって領土の拡張は求めない。」
ソ連は9月にこの憲章に参加した。
◗1945年4月5日、条約を延長しないと通告。しかし、条約は1946年4月25日まで有効。
◗1945年7月26日、「ポツダム宣言」勧告。連合国が日本の降伏を勧告する宣言で、英・
米・中華民国によって作成され、ソ連は後から加わる。
◗1945年8月6日、米軍、広島に原爆投下。8月9日、米軍は長崎に原爆投下。
◗1945年8月9日、ソ連が対日参戦。
◗1945年8月14日、日本は「ポツダム宣言」受諾。(武装解除、非軍事化、民主化等)
ソ連は日本のポツダム宣言受諾後も攻撃を続け、8月28日から9月5日までに北方4島(歯
舞・色丹・国後・択捉)を不法に占領した。
◗1951年9月8日、「サンフランシスコ平和条約」調印(吉田茂首相)。1952年4月28日発
効。ソ連はこの条約に調印しておらず、日本との平和条約は未だ結んでいない。
************************************************************
※諜報戦の中で、いかに正確で大量の情報を獲得し分析しうるかが存亡に影響していることがいつの時代でも同じである。
1945年8月16日、スターリンは北海道北東部(釧路~留萌)を結ぶ直線以北をソ連占領地とするようトルーマン大統領に求めた。しかし8月18日トルーマンは即座に拒否した。
※日ロ間の領土の経緯
・1855年「日魯通好条約」
ロシアは千島列島南端ウルップ島を国境界線として、択捉島以西は日本領であると確認。
・1885年「樺太千島交換条約」
日本はこの条約で千島列島最北の島シュムシュ島からウルップ島までの18島をロシアから
譲り受け、代わりに樺太全土を放棄した。
・1905年「ポーツマス条約」
日露戦争後、樺太南部を譲り受けた。
2023年(令和5年)
*********************
ロシアのウクライナ侵攻2年目
*********************
2月24日で、ロシアのウクライナ侵攻が2年目にはいる。国連では3回目の『国連緊急特別会合』が開かれ、「ロシアに対してウクライナ侵攻即時停戦決議」が提案された。3回目になる決議案は、賛成141か国、反対7か国、棄権32か国、不参加13か国となり、1回目とほぼ変わりない評決になった。この決議案には何ら拘束力はなく、国連の機能不全をたださらけ出すことになったが、手を拱いているわけにはいかないだろう。そもそもプーチン大統領の被害妄想が端を発したのである。核兵器最大保有国に対してどう対処していけばよいか。人類に対しての大命題が投げかけられたのである。
政治家ではこの問題を解決できないだろう。自国の利益、自分の利益を優先する政治家は論議する資格はない。この戦争で勝ち負けはない。プーチンは認めないが、ロシアは2014年前に戻るべきだ。プーチンを説得できる人物はいないのか。
☆☆☆ 喜寿祝い クラス会 ☆☆☆
2024.4.26 ホテル サンプラザ

八年ぶりのクラス会が喜寿祝いの宴😄
お互いちょっと時間が経てば、あの時にタイムスリップ‼「○○ちゃん、▽▽さん、##」と当時の呼び名が飛び交っていた。
話題は体調や???や※※※やら、時間の経つのが早いこと。
卒業後65年。人生100年時代、お互いに健康寿命を伸ばして生きよう😃












😃😄😃😄😃😄😃😄😃😄😃😄😃😃😄😃😄😃😄😃😄😃😄😃😄😃😃😄😃😄😃😄😃😄😃😄😃😄😃
アフガニスタンで65万人の命を救った中村哲医師を思う
😃😄😃😄😃😄😃😄😃😄😃😄😃😃😄😃😄😃😄😃😄😃😄😃😄😃😃😄😃😄😃😄😃😄😃😄😃😄😃

2019年12月4日アフガニスタン東部ジャララバードを車で移動中、武装グループから銃撃を受けて運転手や通訳など5人と一緒に亡くなった。73歳で志半ばでの死は、無念だったに違いない。灌漑事業の進み具合を見回っていた途中のところだった。今一度、中村医師のとてつもなく偉大な足跡をふり返り考えてみたい。
中村医師は九州大学医学部を卒業後、医師として働いていたが、1984年キリスト教海外医療協会から派遣されパキスタン北西部のペシャワールでハンセン病を中心とする医療活動に従事した。
1991年、パキスタンから隣国アフガニスタンの険しい地帯ダラエヌール地区に初の診療所を作り、多くの人々の命を救った。さらに医療活動だけでなく、「水があれば救える命がある。」の信念でアフガニスタンに1600本の井戸を掘り、戦災と干ばつに襲われた国をなんとか救おうとした。
中村医師の活動を支援しているペシャワール会(PMS)について:
1983年9月中村医師のパキスタンでの医療活動を支援する目的で結成された国際NGO(NPO)団体。病気の背景には慢性の食料不足と栄養失調があることから、砂漠化した農地の回復を急務として灌漑水利事業に重点を置いて活動している。診療所、農業事業、灌漑事業、訓練所での技術の普及活動を進めている。この活動費はすべて寄付で賄われている。
1991年医師として派遣されていたパキスタンから、隣国アフガニスタンの険しい山岳地帯ダラエヌール地区に初の診療所を作り多くの人々の命を救っていた。しかも医療活動だけではなく、アフガニスタンに1600本の井戸を掘り、戦災と旱魃(カンバツ)に襲われた国を救おうとした。
2002年アフガニスタンは難民で溢れ、1万人~2万人の難民キャンプもあった。これまで掘った井戸の水位も下がり再掘削に追われた。しかし、パキスタン政府は地下水の枯渇を恐れ、井戸掘りの禁止を命じた。中村医師は大胆な方向転換を余儀なくされた。
2003年『緑の大地計画』で、アフガニスタンの東部を流れるクナール川から全長13キロの用水路を築き水を送り込み乾いた大地を潤す計画である。写真1列目左と中央のもの。
中村医師の言葉『100人の医師よりは1本の水路が必要だ。』









2002年に現地に入り、初期の用水路建設に携わった川口氏は誰も経験のない当時は苦労の連続だったと振りかえった。「最初はスコップと人手で掘っていた。(写真3)何十年かかるのだろうと思った。1日に1ドルか2ドルの日雇いのお金を渡す。彼らにとっては貴重な現金収入だ。最初は100人から200人だったのが、400人から500人へと人手が増えて行った。中村医師は独学で重機の操縦を覚え、また土木工学を学習し水路の建設にあたった。水路そのものも先進国の技術で作っても、現地の人には補修ができない。中村は針金で編んだ籠に石を詰めて形を作る「蛇籠工」を用いることで、壊れても現地で修復できる工法に徹底してこだわった。(写真4)
工事の中でも最も困難を強いられたのが、川から水を水路に取り込む取水口の「堰」の工事だった。大量の土砂の混じる川の水、何度も濁流にのまれた堰。中村医師がたどり着いたのが福岡県朝倉市を流れる筑後川中流にある「山田堰」だった。これは江戸時代に築かれた取水堰である。
現地の人たちも変化が現れ、タリバンの戦闘員だった人や米軍に雇われていた人たちが武器をつるはしに持ち替えて協力するようになった。「自分たちの手で国を立ち直らせたい。また農業をやりたいんだ。」農業ができるように 工事の中でも最も困難を強いられたのが、川から水を水路に取り込む取水口の「堰」の工事だった。大量の土砂の混じる川の水、何度も濁流にのまれた堰。中村医師がたどり着いたのが福岡県朝倉市を流れる筑後川中流にある「山田堰」だった。これは江戸時代に築かれた取水堰である。農業ができるようになれば子どもに食べさせることができる。出稼ぎに行かずに家族と一緒に暮らせるんだ。」現地の人たちの率直な声だ。
『アフガン問題とは、政治や軍事問題ではなくパンと水の問題である。「人々の人権を守るために」と空爆で人々を殺す。果ては「世界平和」のために戦争をするという。いったい何を何から守るのか。こんな偽善と茶番が長続きするはずはない。』(ペシャワール会報)

建設開始から7年たった2008年、13キロの予定だった用水路は、およそ倍の25キロまで伸び、完成した。「アーベ・マルワリード(真珠の水)」用水路。中村医師が手掛けた堰は9つにおよぶ。
両岸には柳の木を植え、根を張り巡らせることで水路をより強固にし、もし壊れれば住人たちが自力で修理を重ねた。
モスクとマドラッサ(学校)を建て、多くの子どもたちに学ぶ機会を与えた。

中村医師の尽力で住民たちの生活は大きく変わった。
「きれいな水が来るようになって、農場で牛に水を与えられるようになった。」
「昔はこの土地で育つ穀物が少なく、アヘン栽培に頼っていた。アヘン栽培のようなイスラム教の教えに反する行動が少なくなった。」と住民たちは語っている。
中村医師が手掛けた堰は、「マルワリード」を含めて9本に及んだ。

ある住人の父親は、自分の子どもに「ナカムラ」と名前をつけた。
カブールの空港で行われた追悼式で、アフガニスタンのアシュラフ・ガニ大統領が自ら中村哲医師の棺を担いだ。
以上の内容は、様々な報道機関の特集を抜粋したもの。「ペシャワール会」は、すべてが寄付によって活動が成り立っている。この寄付は減税の対象にはならない。中村哲医師の崇高な遺志がさらに推し進められるよう考えている人たちは、ぜひ協力を願いたいと思います。
「ペシャワール会」で検索するとわかります。

小学校の遠足と言えば、美流渡の町を過ぎて毛陽町の「毛陽小学校」へ行ったものだ。
2時間くらいかけて毛陽小学校のグランドに着き、ひと遊びして昼御飯だ。男子は大きなおにぎりにかぶりつき、女子は思い思いに友達が集まり弁当を食べる。食事をしている時の顔が1番いい‼またひと遊びをして帰りの途に就く。
「歩け、歩け、あーるけ歩け・・・」歌を歌って帰りの道を歩く。
現在は石碑が建物のあった所に残されている。
校舎跡には、「メープルロッジ」の宿泊施設が建てられ、食事など来訪者がある。写真がその建物である。



年ぶりに会った。去年の「喜寿祝いクラス会」に何年かぶりに出席して、幼馴染の級友と心ゆくまで話したことだろう‼
血圧が高いとのことだが、元気だ。奥さんにもお会いした。
当時住んでいた郵便局の辺りは、うっそうと草や木が茂り、炭鉱の坑口へ続く道は僅かに残っていた。当時のお風呂の跡も広場になっていた。




2024年(令和6年)
◉ 江戸時代の北海道の道路 ◉

1792年(寛政4年)ロシアのラクスマンが修好通商を求めて根室に来航したり、1796~1797年イギリスの船が内浦湾に停泊したり上陸することもあり、幕府は北海道(当時は蝦夷)を東西に渉って大規模な踏査を始めた。
漁業のために入り江の近くに細い道があるだけで、人馬が通れる道はほとんどなかった。ロシアの南下に備えて特に東蝦夷の道路開削が急がれた。

1859年(安政6年)東北地方の6つの藩(秋田、庄内、会津、仙台、南部、津軽)は幕府から北海道の分領、開拓を命じられた。
それまでは、松前藩が渡島半島の南部を統治していたが、その他の領地は幕府の直轄地とは言え、たえずロシアの脅威にさらされていた。その防護を兼ねて幕府は6つの藩に分領した。
松前藩は、他の藩と違い大名知行権は石高による土地の支配権が無く、蝦夷地交易の独占権のみであった。特産物がとれる場所を家臣に与え、その特産物を江差・松前・箱館で換金させた。この場所請負制で藩政を維持した。家臣は次第に商人にそれを委ねるようになった。
その場所請負人が人手を集め道路開削に当たった。江戸時代の北海道の道路は幕府の命を受けた松前藩は、場所請負人たちによって道路開削が進められていった。

▽太平洋岸の道路開削▽
寛政年間から文政年間にかけて、さらに幕末までかけて悪天候では交通不能な道路を新たに開削し、道南の渡島の国(函館)から道東や千島国方面への陸上交通が整備された。函館から択捉末端まで282里(1107.5㎞)。
「長万部ー虻田(豊浦町)」間の道路:-
寛政11年(1799年)松前藩が開削し、享和3年(1803年)津軽藩が礼文華山道とベンベ(弁辺)山道の拡張をした。
長万部<アイヌ語シャマンベ=川尻が横になっているという意味>。豊浦町(農産物や水産物が豊富な町と言う意味)

「室蘭ー幌別」間:-
室蘭ー幌別(ポロペツ=大きい親なる川<アイヌ語>現在の登別):初めは室蘭湾を横切って絵鞆(えとも)に渡り、そこから幌別まで陸路だったが、室蘭から幌別まで陸路で行けるようになった。室蘭市立幌別小学校はダブル円形校舎で有名だった。写真は室蘭発祥の地「絵鞆岬」。
室蘭<アイヌ語モ・ルエラニ=小さな下り坂と言う意味>。

「様似山道」:-
寛政11年(1799年)開削された山道。南部藩が享和2年(1802年)から3年にかけて修繕した山道。約8㎞の山道。
幌満側から西方向へのルート。ルランベツ川を徒渉――尾根線「日高耶馬渓展望地」看板――コマモナイ沢徒渉――コトニ線――オソフケシ。
様似<アイヌ語サンマウニ=枯れ木が海岸に多く打ち上げられているという意味>。

「猿留(サルル)山道と留辺蘂(ルベシベツ)山道」:-
猿留山道は寛政11年(1799年)幕府の公金で開削された北海道<当時は蝦夷>最初の山道。
幌泉(ホロイズミ)<現襟裳町本町>――コロップ――追分峠――日高山脈南端――豊似(トヨニ)岳の山腹――沼見峠――カルシコタン――猿留川を越え――猿留<現字目黒>までの30㎞。[赤い線]
北海道の測量をした伊能忠敬や北海道の名付け親の松浦武四郎が使用した道。
留辺蘂山道は寛政10年(1798年)開削され、国道336号「黄金道路」の前身。
留辺蘂――鐚田貫(ビタタヌンケ)までの8㎞。[青い線]
ルベシベツはアイヌ語で「道が下る川」の意味。ビタタヌンケは「小石川原の砂丘」の意味。

釧路―厚岸間道路:-
釧路ー仙鳳趾(せんぽうし)間35.3㎞は寛政11年(1799年)から12年かけて馬の通行にも支障がない道路を開削した。仙鳳趾ー厚岸間21.6㎞は文化5年(1808年)に開削した。現在の道道根室浜中釧路線の前身。

根室―厚別間道路:-
万延元年(安政後、文久前の元号)(1860年)昆布盛(こんぶむい)<アイヌ語「コムブ・モイ」=水中の石の上に生える草>から厚別(あつしべつ)に至る36.4㎞を開削。
根室(ねむろ)駅<アイヌ語「ニムオロ」=樹林>から昆布盛駅まで15分、昆布盛駅から釧路駅まで2時間。

▽日本海岸の道路開削▽
「太田山道」、「狩場山道」:-安政4年3月起工、太田山神社のある太田山を中心にセキナイ<シュプキナイ=茅沢>からラルイシ(良瑠石)までの47㎞を開削、ついで狩場山道に着手し、須築から島牧村原歌のコタニシに至る道を開削した。

「雷電嶺」:-
安政3年(1856年)アフシタ以西4㎞を磯屋場所請負人、アフシタ以東8㎞を岩内場所請負人が開削した。雷電峠はりょうばしょの境を越える道で、国道229号線の前身。以前から山中に温泉が湧くことが知られており、現在の朝日温泉。

「余市山道」:-
文化6年に開削された岩内から余市に至る道で、稲穂峠がある大変な難所だった。その後荒廃したため、安政3年から4年にかけて改めて開削。その距離は50㎞近くになった。現在の道道豊岡余市停車場線から分岐する舗装道路の前身。

「厚田ー増毛道」:ー
安政4年、濃昼山道10.5㎞、浜益から増毛までの35.3㎞が開削され、海岸線には雄冬山道も開削された。
濃昼と増毛の中間には送毛山道(現在は送毛トンネル)があった。
現在の国道231号の前身。
「留萌ー石狩川」:ー
文化5年、留萌から恵岱別を経て石狩川流域に出る98.2㎞を開削し、石狩川を舟で下り、江別太へ出て、そこから千歳に向かうか石狩に下ることが出来た。雨竜越と言われている。
▽道央の開削道路▽
太平洋側の勇払から千歳の至る経路で、勇払から美々までは勇払沼、美々川を舟で遡り、美々から美々から千歳までは文化年間に7.9㎞が開削された。国道36号の道筋。


「勇払ー美々」「美々ー千歳」:-
勇払から美々川を舟で遡り、美々から千歳まで文化年間に開削され国道36号の道筋。

「札幌越(千歳新道)」:-
安政4年、銭函ーホシポッケ間、ホシポッケー島松間、島松ー千歳間がそれぞれ開削された。
銭函から現在の札幌市内まで国道5号と道道宮の沢北1条線の前身。札幌市内から千歳までは国道36号と道道江別恵庭線の前身。
▽道南地域の道路開削▽


「福山ー上ノ国」:-
津軽海峡に面した福山から千軒岳を経て、上ノ国湯ノ岱に至る43.2㎞が安政4年に開削された。現在の道道石崎松前線の前身。
「木古内ー上ノ国」:-
木古内から上ノ国に至る31.4㎞の道で、現在の道道江差木古内線の前身。

「木古内ー函館ー鹿部」:-
安政3年、藤山から軍川の山道が開削され、鹿部に生魚を買い出しに行き日帰りが可能になった。

「長万部-黒松内」:-
長万部川沿いに北上し、黒松内から歌棄や寿都に至る道で、現在の道道寿都黒松内線の前身。23.6㎞。
「黒松内ー追分」:-
7.9㎞の道。
「追分ー寿都」「追分ー歌棄」:-
追分で分岐し、寿都まで8㎞。歌棄てまで4㎞の道路。
▽道東地域の道路開削▽



「標津ー斜里」:-
文化元年前後(1804年前後)、標津から標津川を遡り若生<ワツカオイ>を経て斜里に至る道。
「庶路ー阿寒湖西岸ー女満別<ニマンベツ>ー網走」:-
文化5年(1808年)から同年7年(1810年)にかけて180㎞の開削道路。
◉明治時代の開削道路は「囚人道路」◉


昼夜を問わずの過酷な労働と満足な食事も与えられない不衛生な小屋暮らし、足には逃亡を防ぐために足に鎖をつけられたままでの酷使され続けた囚人たちの中から多くの犠牲者が出た。病死や惨殺されていった囚人たちの屍は、現場近くにそのまま捨てられて風雨にさらされた。当時の囚人たちが土を盛るようにかぶせられて埋葬されたと言われている。
この「土まんじゅう」は、後の入植者たちによって見つけられ、「鎖塚」と呼ばれるようになり、鎖でつながれたままの二人の白骨も発見された。
札幌と岩見沢間は囚人道路ではない。

「上川道路(三笠ー旭川)」:-
市来知(三笠)と忠別(旭川)を結ぶ道路で「石狩道路」とも呼ばれる。1886年(明治19年)北海道初代長官岩村通俊が、この間88㎞の開削を命じた。空知川を境に旭川までを樺戸集治監(月形)、三笠までを空知集治監(三笠)が分担した。
現在の美唄ー滝川間の日本一長い直線道路29.2㎞は、3か月で完成させた。
「北見道路(旭川ー網走)」:-
旭川ー北見間は「北見道路」(現在の国道39号)という道路名。明治政府が軍事道路として建設したもの。開削工事には網走監獄や空知集治監(月形町)から多くの囚人たちが駆り出され、昼夜を問わず無数の蚊やブヨに襲われ、また狼や羆の恐怖と闘いながら、昼夜を問わず突貫工事が進められた。病気や怪我人が多数出たが記録がない。1886年(明治19年)5月の着工から4か月余りで仮道が全線開通。1887年(明治20年)から本工事が行われ、1889年(明治23年)完成した。
囚人道路の時代背景:-
明治維新後、明治政府が進める改革政治に対する不満や意見の違いから、日本各地で内乱が起きた。「佐賀の乱(1874年)」や「西南の役(1877年)」。「国賊」と呼ばれた多くに人々が逮捕されていった。また戦乱で国民の生活は困窮し、犯罪者が後を絶たず1885年(明治18年)には犯罪者数が9万人になった。これまでの集治監では収容人数を超えたため、新たな集治監を作る必要に迫られた。内務省長官伊藤博文は北海道への集治監設置を考えた。
1879年(明治12年)伊藤博文の「徒流両囚発遣地先以御予定相成度伺」により屯田兵入植の前に開墾させるため、多くの囚人を移送する政策をとった。
明治政府は、未開地であった北海道に国賊や政治犯として逮捕された囚人を隔離しておくことは好都合であり、道路工事の作業員として使えば費用が安く上がるという理由から集治監(刑務所)を北海道に設置した。明治14年(1881年)石狩国樺戸郡須別太(スベツブト=月形町)に「樺戸集治監」、明治15年石狩国空知郡市来知(イチキシリ=三笠市)に「空知集治監」、明治18年釧路国川上郡熊牛村(標茶町)に「釧路集治監」、明治23年釧路集治監の分監として網走に「網走囚徒外役所」、その後下帯広に釧路分監帯広外役所」が作られた。
1885年(明治18年)、伊藤博文の側近金子堅太郎が北海道を視察した後「北海道三県巡視復命書」では道路開削のために囚人を利用すること進言をした。






●鎖塚慰霊碑●
札幌から大雪を越え網走に達する中央横断道路は、「釧路集治監網走分監」と「空知集治監」の1100人余りの囚人を使い、特に北見~網走間は1891年4月に着工し12月に160㎞を完成させた。満足な食事も与えられない環境で、逃亡を防ぐために両足に鎖で4㎏の鉄球がつけられ、二人一組で繋がれた。死ぬ時も鎖をつけられたままであった。
囚人たちが死亡した囚人仲間を弔うために死んだ囚人の上に土饅頭として目印にした。この劣悪な難工事で死んだ囚人は200人を超えたと言われている。
後に入植者が鎖のついた人骨が見つけたことによって「鎖塚」と呼ばれるようになった。

以前網走に行った時、網走刑務所博物館を訪ねました。この刑務所には政治犯が多く収容されていて、高学歴者が多くいた。展示室には沢山の掛け軸があり、その筆跡の力強さや素晴らしさを見ることができました。訪ねた目的が実はこのことがあったのです。そのほか日記のようなものが、筆字で流れるような文字で書かれていたことが印象深かったことと憶えています。ぜひ訪ねるべき場所です。
左の詩は、その時の囚人の心境を詠んだものだが、道路開削に駆り出された囚人たちは現場の掘立小屋で過酷な重労働の連日で、満足な食事も与えられず病死していく者が多く出た。日記を書く用具は与えられることはなく当時の記録はない。
ここで18世紀後半から19世紀にかけて外国や日本の状況を時系列で見てみよう!




◉北海道の鉄道と炭鉱◉ 北海道の鉄道は炭鉱と密接な関係があったことを憶えておこう‼

・明治2年(1869年)明治政府は北海道の資源開発のため、北海道開拓使(官庁)を設置。
黒田清隆開拓次官が海外から外国人技術者ケプロンを招き資源調査。
三笠上流の炭田の埋蔵量が多く殖産興業政策として有望と判断する。
ライマンを招き炭田の開発計画を立案させる。
ケプロンの案=幌内―室蘭<鉄道>
ライマンの案=幌内―幌内太(幌向)<鉄道>・石狩川<舟>―小樽港 ライマンの計画が経費が掛からない
・明治11年(1878年)開拓使がライマンの案を承認
・明治12年(1879年)クロフォードが幌内~幌内太の測量開始
*問題点*幌内太付近は湿地が多い、石狩川の冬季の結氷で150日程度の利用しかできない
クロフォードは計画を変更、幌内太―小樽<鉄道>
・明治13年(1880年)1月小樽市若竹第3隧道から着工、10月24日手宮桟橋―熊碓第4隧道間で「弁慶号」による試運転、11月28日手宮―札幌間開通 官営幌内鉄道開通
(手宮駅-開運町駅-朝里駅-銭函駅-軽川駅-琴似駅-札幌駅)
・8月30日明治天皇北海道巡幸で初のお召列車「しづか号」が運行

「小樽ー幌内」線:
日本で3番目の官営幌内鉄道として運行された。(1880年明治13年11月28日)
1889年(明治22年)11月18日、堀基が中心となって「北海道炭礦鉄道会社」を設立。
政府から幌内炭鉱と官営幌内鉄道の払い下げを受け、炭鉱従事者に囚人を使役できる特権を与えられた。
堀基=薩摩藩士で幕府軍と戦った。1869年開拓使に移り、屯田事務局長などを歴任し、薩摩閥を見せつけ先輩の黒田清隆と共に樺太に渡り、ロシアとの交渉に当たった。1882年開拓使が廃止された後、実業界に転身。小樽で「大有社」(北海道初の商社)を設立。函館の商人とは「北海道運輸会社」(後の日本郵船の一部)を設立し、海運業に進出。1888年後輩の永山武四郎が北海道長官に就くと、道庁の理事官を辞して「北海道炭礦鉄道」を設立した。幌内炭鉱、官営幌内鉄道の払い下げなどは永山長官らと示し合わせたもので疑獄事件に等しいものであった。晩年は私費を投じて北鳴学校(後の札幌中学)を開いた。1894年勅選により貴族院議員に就く。1912年、69歳で没す。
1896年(明治29年)、北海道鉄道敷設法が公布・施行されて北海道庁が鉄道建設にあたった。明治政府の富国強兵政策の一環でもあった北海道の炭鉱開発と鉄道敷設は一致した。

「北海道鉄道」(函館ー小樽間民営鉄道)
1896年(明治29年)「函樽(かんそん)鉄道」として、北垣国道(4代北海道庁長官)が長官退職後に会社を設立。
1900年(明治33年)「北海道鉄道」に改称。
1902年(明治35年)函館駅∼蘭島駅を開設。
1903年(明治36年)塩谷駅∼小樽中央駅を開設。
1904年(明治37年)小樽中央駅を高島駅に改称。10月函館駅∼高島駅間が全通。
1905年(明治38年)高島駅∼小樽駅間が開業し、北海道炭礦鉄道に接続。
1906年(明治39年)北海道炭礦鉄道との直通列車函館駅∼札幌駅間が運行開始。

岩見沢JRレールセンター:-
1892年(明治25年)、北海道炭礦鉄道の室蘭線開通後、1898年9月着工翌年8月に完成した車両製造と修理のため建築された施設。ファサード頭頂部に五稜星のマークは北海道炭礦鉄道の社章で、JR北海道の現在も使用されている。2010年(平成22年)事務所が準鉄道記念物に指定された。現在もJR 北海道各線の使用されるレールの加工を一手に引き受けており、青函トンネルのロングレールもここで製造された。
1896年(明治29年)、北海道鉄道敷設法が公布・施行されて北海道庁が鉄道建設にあたった。明治政府の富国強兵政策の一環でもあった北海道の炭鉱開発と鉄道敷設は一致した。

「室蘭線」:-
1892年(明治25年)8月1日、北海道炭礦鉄道室蘭線が室蘭駅ー岩見沢駅間で開業。空地域で産出された石炭を室蘭港へ運搬した路線。1906年(明治39年)10月国有化され、官設鉄道となる。
1923年(大正12年)12月10日、国有鉄道「長輪線」として長万部駅ー静狩駅間が開業される。1928年(昭和3年)9月、静狩駅ー伊達紋別間が延伸開業し、1931年(昭和6年)長万部駅ー岩見沢駅間を室蘭本線とした。
写真は室蘭駅
「夕張線」と夕張の炭砿:-
明治30年代から石狩石炭会社が炭鉱開発をし、1909年(明治42年)には熊ノ沢ー鹿ノ谷ー若菜辺間で専用の鉄道使用を開始した。1920年(大正9年)、北海道炭礦汽船が石狩石炭を吸収し石炭輸送のために夕張鉄道株式会社を設立。1926年、新夕張ー栗山間開業。1930年、(昭和5年)、栗山ー野幌間開業。
起点「野幌駅」、終点「夕張本町駅」、19駅。 総延長53.2㎞。 多くの北炭専用鉄道が接続。
1975年(昭和50年)「夕張線」廃線。

夕張市は、1960年(昭和35年)には北炭夕張鉱業所・北炭平和鉱業所・三菱大夕張鉱業所の3大鉱業所があり、関連した北炭機械工業所(鉱山・産業機械製造)、北炭化成工業所(コークス・化成品製造)ができて、ピーク時の人口は116,908人になった。
1990年(平成2年)、最後まで残っていた三菱石炭鉱業南大夕張炭鉱が閉山。
2007年(平成19年)、財政再建団体となり財政破綻となる。
2024年(令和6年)の人口は6348人。
写真は最盛期の駅周辺と遠方は炭住街。
相次ぐ炭鉱事故
1908年(明治41年)、新夕張炭鉱でガス爆発事故、死者93人。
1912年(明治45年/大正元年)、夕張炭鉱で4月29日爆発事故、死者269人。12月23日爆発事故、死者216人。
1913年(大正2年)1月13日、夕張炭鉱で火災発生事故、死者53人。
1914年(大正3年)10月3日、夕張炭鉱でガス爆発事故、死者16人。11月28日、新夕張炭鉱でガス爆発事故、死者423人。
1920年(大正9年)1月11日、新夕張炭鉱で爆発事故、死者36人。6月14日、夕張炭鉱北上坑で爆発事故、死者209人。
1938年(昭和13年)、夕張炭鉱天竜坑で爆発事故、死者161人。
1940年(昭和15年)1月6日、真谷地炭鉱で爆発事故、死者50人。
1960年(昭和35年)、夕張炭鉱第二坑で爆発事故、死者41人。
1965年(昭和40年)、夕張炭鉱第一坑で爆発事故、死者62人。
1968年(昭和43年)、北炭平和鉱で坑内火災事故、死者31人。
1981年(昭和56年)、北炭夕張新炭鉱ガス突出事故、死者93人。
1985年(昭和60年)、三菱南大夕張炭鉱でガス爆発事故、死者62人。
記録に残されているもの以外に多くの死者がいたことは推測できる。
当時の雇用形態
炭砿を所有する会社がすべての従業員を雇用するのではなく、下請けの会社に採炭業務などの多くを任せていた。さらに下請け業者は従業員を集めるために、斡旋業者に任せ2重・3重の搾取がなされた。その中には朝鮮半島から連れてこられた朝鮮人も多くいた。また囚人も従事させられた。これが当時の雇用形態で、鉄道建設現場での「タコ部屋」もその最たるものであった。

「上川線」
1898年(明治31年)7月、空知太ー旭川間開設。
「天塩線」、「十勝線」
1900年(明治33年)8月、「天塩線」旭川ー士別(宗谷)間開通、士別ー名寄間延伸開通。
「十勝線」旭川ー下富良野(帯広)間開通、下富良野ー鹿越間延伸、鹿越ー落合間延伸開通。
写真は旭川駅

「十勝線」(旭川ー帯広):
1897年(明治30)年、6月に着工。旭川川から起工された工事は数々の難工事があり4年かけて3分の2にあたる南富良野村落合まで到着。しかし、この先は石狩と十勝の境界線に聳える標高1000~2000mの「日高連峰」越えの最大難所が待ち受けていた。様々な路線の検討がなされたが、トンネル建設を避けて通ることはできなかった。1901年(明治34年)「狩勝隧道(954m)」と「新内(にいない)隧道(124m)」の掘削作業が始まった。この工事は日露戦争の途中2年間中断し、1907年(明治40年)9月の完工。十勝線と並行して建設されていた釧路線(帯広ー釧路)と繋がり、11月に旭川ー釧路間が全面開通した。
1966年(昭和41年)10月、根室本線の新ルートが開業し、新たに建設された「新狩勝トンネル(5790m)」に代わった。

「釧路線」
1901年(明治34年)7月、釧路ー白糠間開通。
1903年白糠ー音別間開通。音別ー浦幌間延伸、浦幌ー豊頃間延伸、
豊頃ー利別間延伸開通。
写真は釧路駅

「網走線」(池田~北見経路):
1907年(明治40年)3月、凋寒側(しぼさむ)<1906年凋寒村=現在の池田町>より起工された。さまざまな路線案の中、北見一帯に広がる膨大で良質な木材資源に目をつけた本州資本と連携する地元代議士の思惑が反され、この路線が選択された。沿岸で伐採された木材をこの路線で池田町から久代まで運び、釧路港からその木材を積み出す計画です。
陸別までははさしたる問題もなく敷設が進められたが、釧北峠(現池北峠)声の工事は人跡未踏の原生林で物資の補給が極めて困難だった。置戸町内に達したところで「マラリア」が発症した。建設業者によって病院が建てられたが、治療薬は十分でなく死者が多数発生した。「タコ部屋」の過酷な労働の中でさらに死者の増えていく中、1912年(大正元年)10月、池田~網走間(190㎞)が完工し網走線が全面開通した。
工事中の1910年(明治43年)、建設業者が施主となり置戸町内の線路脇の丘の上に殉職者を慰霊する碑が建てられた。

「北見線」
明治末期、建設中の「網走線」を見越して湧別を経由し名寄まで延伸する計画が進められていた。この区間はオホーツク海沿いの割合平坦で距離は80㎞程であった。しかし、遠軽の大地主や地元代議士の活動で、直前でルートの変更をして、距離も5割以上長く「留辺蘂ー生田原ー遠軽」経由の山越えのルートが採用された。

「常紋峠」
この工事の全線を4工区に分け、3つの業者が請け負った。元請は大手の土建業者で、さらにその下に下請け業者があり直接現場を監督するのはこの下請け業者が当たった。したがって、何段階にわたって搾取が働き工事従事者に渡る金銭は少なく、監視が厳しい過酷な「タコ部屋」労働の下で命を落とす者が多くいた。当時は本州や中国や朝鮮から連れてこられた従事者が多くいた。違法ともいえる労働状況に国・警察も目をつむりますます異常な状況になって行った。

「常紋トンネル」
常呂郡と紋別郡を隔てる常紋峠に開削された「常紋隧道」は、延長507mで長いトンネルではないが掘削工事は難航した。この湧別線敷設工事は全線を4工区に分け、3つの土建業者が分担し請け負った。限られた好機で限られた予算内で完工できるのは「タコ労働者」を使役する下請け業者以外いなかった。しかも「労働者からの搾取」の問題もあった。タコ労働者の中には前借金の返済で工事従事者となった者が多数おり、過酷な労役に耐えていた。しかし、食費のほかに日用品や作業用品まですべてを購入せねばならず、市価の数倍になる価格で購入することで日銭は減り逆に借金がかさむ仕組みになっていた。病死や逃亡に失敗し虐待され死亡した労務者は、工事現場のトンネルの中に埋められていった。1912年(明治45年)3月着工された工事は、1914年(大正3年)10月完工した。
しかし、この工事で埋められら百数十名の遺体は未だわかっていない。

昨年12月6日岩見沢市立病院に入院しました。入院生活が初めてで、いい経験になりました。
急性の黄疸症状が出て、直ぐに手術。胆管の上部が詰まっていて、胆汁が流れない。胆管にステントを挿入したが、流れが良くない。そこで肝臓に直接管を刺しこみ、腹から管を出し胆汁を排泄した。1日2袋、溜まった胆汁が体外に排泄された。20日までこの排泄が続く。溜まった胆汁が無くなった後、21日に胆管に新しくステントを取り付け、胆汁の流れをよくした。その後、患部を精密検査に出した後、2024年(令和6年)1月9日、担当医師から本人と家族に「胆管癌」と告げられた。「肝臓と胆管の繋ぎ目に2㎝のがんがあります。今後の対応としては、『外科的措置・抗がん剤投与・放射線治療・なにも治療しない』がありますが、高齢(88歳)ですので、治療にしても薬の投与も大変な負担になりますので、私は勧められません。むしろ余生をゆっくり過ごされた方がよいかと思います。」と言われた。
迷わず「何もしないで余生を送る」を即答した。妻が老人施設に入居しているので、自分で食事の献立を考え、車で買い物に行ってる生活。何よりも「免疫力を高める食事の献立を考えての毎日」。肝臓の働きと胆汁の流れをよくする薬を飲んでいる。月1回の血液検査があり、結果は悪くはなっていない状況。

みんな元気ですか!
こんな様子で過ごしていますよ。
スマホで asahishogaku.flips.jp で検索すると見れます。
メールアドレスは ji6ttkhs@gmail.com です。